ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします
- TOP
- 国際人権基準の動向
- 国際人権ひろば
- 国際人権ひろば No.180(2025年03月発行号)
- アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)設立30年を振り返って
国際人権ひろば No.180(2025年03月発行号)
特集:ヒューライツ大阪設立30周年記念事業
アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)設立30年を振り返って
財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)は、1994年12月に大阪市港区弁天町のORC200(現在の大阪ベイタワー)に開設された。私が国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)を退職し、ヒューライツ大阪の所長として赴任したのが2006年5月であったので、設立の詳しい経緯については、ヒューライツ大阪の記録をたどるほかない。
記録によれば、1993年4月に、それまですでにあった市民団体などの人権センター設置の強い要望を受けて、大阪府・大阪市・民間団体による基本整備計画策定委員会が設置され、同年11月には、大阪府市長会ならびに大阪府町村長会がセンター設立に賛同し協力することを決定した。大阪府、大阪市を筆頭に、府内の全市町村、部落解放同盟や労働組合等多くの民間団体からも、基本財産となる出捐金(寄附金)が寄せられた。その額合計約8億8千万円であった(1。人権団体の基本財産として、これは異例の規模であったのではないか。さまざまな関係者の多大の尽力と貢献があったことは想像に難くない。
想定外の変革
ヒューライツ大阪の運営は、当初、主に大阪府と大阪市の資金的および人的支援に依存していたが、2008年2月、橋下徹氏が大阪府知事に就任して「財政非常事態宣言」を発して、それまで府が出資してきた法人への補助金を廃止することを前提に見直すという方針を打ち出した。同年6月には大阪府が財政再建プログラムを公表、そこで、ヒューライツ大阪に対しては、2009年度から補助金の廃止と府からの派遣職員引上げが確定した。これを受けて、大阪府と同じ条件でヒューライツ大阪に補助金と派遣職員を出していた大阪市も事業支援から撤退することを決定した。大阪府、大阪市は、それぞれ独自の人権行政を行うことで事足りるとしたのであろうか。
こうして、ヒューライツ大阪は、以後行政から独立して、基本財産を取り崩しながら、事業を進めることになった。これは、一市民社会団体としての再出発であり、組織の実質的変革であった。
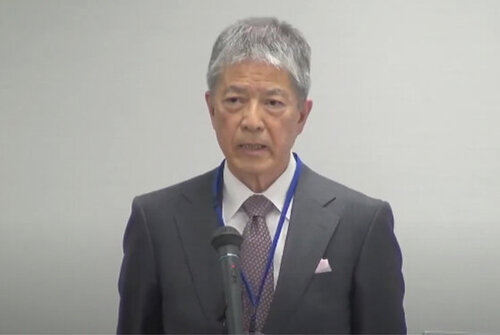
30周年記念事業であいさつする白石会長(2024年12月7日)
大阪府と大阪市の事業支援廃止が決まった時、所長としてことの重大性に危機感を抱き、同時にやり場のない失望感に襲われた。その時の想いを『国際人権ひろば』No.80(2008年7月)の「人権さまざま」に綴っている。
このたびの公的関与の打ち切りにはどのような判断があるのか。ヒューライツ大阪の存在意義もその掲げる目標の重要性も認めないということなのか。ヒューライツ大阪の目標とは、大まかにいえば、国際社会、特にアジア太平洋地域の人権保護促進に貢献することと、日本国内、特に大阪で国際人権の理解と啓発に努めることである。この目標の大切さは認めても、ヒューライツ大阪がその実現のためにいい仕事をしてきたとは認めない、だからもう関わる必要を認めないということなのか。
(中略)
行政が人権に関わるとき、人権はその本来の意味を失う危険がある。人権は、弱い立場にあるものが強い者や権力に対して自らを護るために抵抗し、要求するとき、その拠り所となる。そのために人権行政は、国にとっても行政にとっても危険をはらんでいる。権力に立ち向かう者を支える人権でもある。人権意識の高い市民を育てれば、その市民に監視される行政である。それだけの理解も覚悟もないままに人権行政を掲げるのは、その時々の流れにしたがっていただけ、口先だけの「人権行政」。人権の仕事は、効率を求めることでも、「人を大切にする」ことを否定する世論の流れに迎合することでもない。行政にもの申すことのない人権、市民の間の関係をとりもつだけの人権、思いやりと心の大切さを説くだけの人権は、人権の脱け殻ではないか(2。
この文には、私の中で大阪府、大阪市の人権行政に対する疑念が沸き起こっていたことが伺える。
ヒューライツ大阪はその後、経費削減のための事務所移転や事業の見直しなどを行ない、2011年には公益法人制度改革のもとで新たな定款による一般財団法人に移行した。新たな定款では、大阪をはじめ日本社会で、国際人権基準の理解と人権意識の向上を促進することがヒューライツ大阪の主な使命となった。
私は、2015年6月に所長を退任、2016年に武者小路公秀氏の後を引き継いで会長となって今日に至っている。現在は、副会長、所長、事務局長が、これからのヒューライツ大阪のあり方を見据えながら組織運営を担っている。組織運営で喫緊の課題となっているのが、将来のための資金確保と事業の再編である。
人権関連事業については、ヒューライツ大阪がこれまで一貫して、人権情報の収集、分析、発信、人権教育・啓発活動などに力を注ぎ、一般市民の人権理解、意識向上と、人権に関わる市民団体(NGO)とのより緊密な協働の向上など、人権情報センターとしての業績を着実に上げてきた。
世界人権宣言の人権
日本社会で人権が普通に語られるようになってから、かなりの時が経つ。しかし人権が本当に理解され、社会で広く賛同を得ているとは言い難い。
ヒューライツ大阪がこだわってきた人権は、国際基準の人権であり、その源となるのが、1948年に国連総会で採択された世界人権宣言である。これは、すべての人間が等しく持つ人権について世界中の国と人びとに向けられた極めて重要な宣言である。
世界人権宣言の第1条は、
「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」
とし、
第2条1項には、
「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」
とある。
この二つが人権とは何かを実に簡潔に、また本質的に言い表している。
いまだに、これが実現されていない社会、人権が充分に保障されていない社会が世界にはあまりにも多く、状況は深刻である。
国がそこに住む人々の人権を積極的に護らず、促進しない社会。力を持つ組織、個人が人をおとしめ、搾取し、憎み、傷つける社会。さまざまな理由で差別を容認する社会。このような社会は、「すべての人が人として大切にされる」社会ではない。
ヒューライツ大阪が目指す人権のための働きは、このような現実を変えようとするものである。
人権の危機-個別課題と構造的課題
世界各地で深刻な事態が続く。2022年に始まったロシアのウクライナ武力侵攻、2023年10月ハマスのイスラエル武力攻撃とイスラエルのガザへの報復攻撃をはじめとして、平和が損なわれた世界で子どもを含む多くの一般人が犠牲になっている。そして、民主主義を標榜してきた国々で、また日本でも政治に対する信頼が損なわれ、民主主義体制の危機が取り沙汰されている。信頼回復のために政治改革・社会変革の必要性が高まるばかりである。
これらの問題は、取りも直さず人権に深刻な負の影響を及ぼす。人権課題は、社会で個人と個人の関係で起こる問題であるとともに、広く社会の体制や構造に起因する問題でもある。人権は、広く政治、経済そして社会の課題に関わることを留意したい。
これからのヒューライツ大阪は、個別の人権課題とともに、世界の現状?武力紛争、戦争、民主主義の機能不全、経済的格差と不公平、ウイルス性感染症の世界規模の蔓延、気候危機に伴う甚大災害の常態化など?を構造的課題としての人権の視点からとらえ、人が大切にされる社会、人権が尊重される社会の実現を求めたい。
人権を知らせ、守り、促進することに寄与するために、ヒューライツ大阪の仕事に終わりはない。
<脚注>
1)
https://www.hurights.or.jp/japan/announcing/10_syutuen.pdf
2)
https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2008/07/post-27.html
