ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします
- TOP
- 国際人権基準の動向
- 国際人権ひろば
- 国際人権ひろば No.181(2025年05月発行号)
- フチとエカシに昔の話を聞きに行く
国際人権ひろば No.181(2025年05月発行号)
人権の潮流
フチとエカシに昔の話を聞きに行く
著者は2022年に発足した「森川海のアイヌ先住権を見える化するプロジェクト」(以下、森川海研)(1に2023年春から参加し、約2年間にわたり北海道各地でアイヌ民族のフチ(尊敬すべき年配の女性)とエカシ(尊敬すべき年配の男性)に聞き取りを行ってきた。和民族(以下、和人)マジョリティの立場で参加し、試行錯誤した日々をふりかえり報告する。
どのように聞き取りをしているのか?
森川海研では、以下2つの前提に基づき、アイヌ民族が有する「先住権」を文献調査や聞き取り調査を通して「見える化」し、発信することを目的に活動している。
- アイヌ民族が歴史的に有してきた、土地・領域・自然資源・環境に対する諸権利を、少なくとも最近150年あまりにわたって、日本国家の植民地主義に根ざしたさまざまな政策が不当に妨げ続けている。
- 同時期に日本国家が始めた大規模な植民・開発政策が、北海道の森や川や海の生態系に負の影響を与え、自然資源の潜在的価値を著しく低下させてしまった。
聞き取り調査では、アイヌの民族としての土地や資源の使い方(難しくいうと土地権や資源権の本来のあり方)を、フチとエカシへの聞き取りを通して明らかにしようとしている。
話し手は、アイヌ民族のメンバーの推薦や紹介を元に決定することが多く、活動家や文化伝承者として著名な方だけでなく、知人・友人のご家族や地域の方など、市井の人として生きて来られた方も含まれる。そして聞き手は、アイヌ民族を含む複数のメンバーで実施することを基本としている。話し手は70代後半~90代の方なので、必然的に若い世代が話を聞くことになり、世代間の対話や継承のきっかけになっているのではないかと思う。
この方法についてあるアイヌ民族のメンバーは、「(被差別体験や生活苦など)本来は隠しておきたかったこと、言葉にするのが辛いことや話したくないことでも、アイヌ同士だから言えることがあると感じる」と話す。一方、和人のメンバーは「(植民地支配をした立場なので)聞けないこと、聞きにくいことがたくさんある。(アイヌ民族のコミュニティに属していないため)聞き取りで初めてお会いする方が多い。アイヌのアイデンティティを持つメンバーが一緒にいてくれるのが心強い」と話す。
著者が同席した聞き取りでは、話し手が和人を「シャモ」(2と表現した後、著者らに気遣ってか「和人の方」や「シサム」と言い直す場面がしばしばあった。一方、強制移住の歴史に触れたのち、著者らに対して「本当にろくでもないことをした和人の子孫だよ、あなた方は」と語った方もいた。また、現代のアイヌ民族の運動や取り組みに対する葛藤を語る方もいた。和人が同席することで話しにくいこともある一方、あえて話しておきたいことや、アイヌ民族のコミュニティの中では話しにくいこともあるのかもしれないと感じることがあった。

フチとエカシのストーリー
同意を得ながらゆっくり進める
聞き取りの場でお話しいただいたことは、内容を整理して文章化し、さらに詳しく聞きたいことや確認すべきことをメンバー間で話し合ったのち、再聞き取りする。多い方だと、再聞き取りを3、4回行うこともあった。そして、最終的には対面で全文を音読し、ご了解いただけたものをウェブサイトに公開する。FPIC(3に基づき、話し手に確認し同意を得ながら進めている。
ちなみに、話し手とのやりとり方法はすべてお手紙(郵便)と電話、対面である。広大な北海道においては、宿泊を伴う聞き取りもたびたびある。メールやオンラインでの迅速なコミュニケーションに慣れ切っていた著者は、当初は「もどかしさ」を感じたが、話し手の立場に立てば、この方法が最も安心できるものであった。そして、対面でお会いする機会が増えることで、お茶やお食事をご一緒したり、ご自宅でお写真やアイヌの着物を見せていただいたり、地域のアクティビティや飲み会に参加することができ、結果的には話し手の背景をより理解することができたのではないかと思う。
「先住権」が見える化できない!?
実は、聞き取りを始めて早い段階で、話し手の語りから「先住権」を直接「見える化」するのは困難だということがわかってきた。というのも、話し手たちは日本政府による同化政策が浸透した環境で生まれ育ち、生業、言葉、食事、住居など和人とほぼ同様の生活様式の中で生きてこられたからである。
とはいえ、家族やコミュニティの中で伝えられてきたアイヌプリ(アイヌ式)の「行い」が確かにあるということ、和人の入植と開発によって地域の自然環境が大きく変化したこと、そして、曾祖父母や祖父母の時代からの権利回復の闘いを伝え聞いたり見聞きしたりしていることをお聞きすることができた。
メンバーと話し合い、強引に「先住権の話」としてまとめるのではなく、以下の3つを柱に「先住権につながる(かもしれない)話」としてまとめていくことにした。
- ライフヒストリー(生活史)
- 「開発」と暮らし・環境の変化
- 抵抗と闘い-権利回復に向けて
1、2からは、その人の人生にどれだけ日本政府の政策や和人入植者の行いが影響してきたのを知ることができるのではないかと思う。3の「抵抗と闘い」とは、権利回復に向けた「その人なりの闘い」のことである。話し手の多くが、歌や踊り、刺繍、料理、アイヌ語などのいわゆる「文化活動」を通して、まず、個人としてアイヌのアイデンティティを回復・獲得されてきたことがうかがえた。また、アクティブに活動するようになったのは「50代になってから」という方が多かった。一般的に想像される「抵抗と闘い」とは違うかもしれないが、「その人なりの闘い」を知ることができるのではないかと思う。

報告会に登壇した聞き取りチームのメンバー。
左から川合蘭、井上千晴、著者
一人ひとりの人生のお話から
2025年3月現在、10名の聞き取りを「フチとエカシのストーリー」と題してウェブサイトに公開している。2024年12月には報告会(4が開催され、参加したメンバーのひとりは「わたしたちが紹介しているのは一人ひとりの人生の話で、一般的なアイヌ民族の歴史の話ではありません。だからこそ共感できる部分もたくさんあると思うし、たとえ共感できなくても、より対等な目線でその人の人生や生活を知ることができるのではと思う」と話した。
このように、非アイヌ民族の読み手へは、日本政府および和人入植者の行いとその影響、不幸な歴史や現在につながる不都合な真実について理解すると共に、同時代を生きるアイヌ民族のことをステレオタイプやファンタジーに押し込めずに知ってほしいと願っている。そして、アイヌのアイデンティティを持って生きる人たち、これから先住権を獲得しようと活動する人たちには、「その人なりの何か」を見出してくれたらという願いがある。未だ対等とはいえない立場にあるアイヌ民族と和人だが、この聞き取りが森川海研の目指す「双方が同じテーブルについて議論して、お互いに理解と関与を深めあい、『歴史的な不正義』を解消する道を一緒に探って」(5いくことの一助になればと思う。ふりかえれば、聞き取りのプロセスはまさにこの繰り返しであった。
聞き取りは継続中なので、ぜひお読みいただき、フチとエカシの人生に触れると共に、感想やご意見をいただければ幸いである。
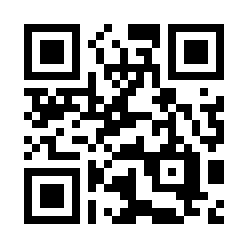
森川海研ウェブサイト https://mori-kawa-umi.com/
<脚注>
1)
The David and Lucile Packard Foundationの助成を受けアイヌ民族、和人、人権・環境・教育NGO関係者が参加したジョイントプロジェクト。https://mori-kawa-umi.com/
2)
シャモ/シサム:どちらもアイヌ民族からみた和民族(和人)の呼称。シサム(隣人)に比べるとシャモは俗語や蔑称としての意味合いを含むといわれることが多いが、地域や家族、個人によっても使い分けは異なる。
3)
FPIC(エフピック):Free Prior Informed Consent:自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意
4)
さっぽろ自由学校「遊」2024年度後期講座「先住民族の森川海に関する権利5-アイヌ先住権を"見える化"する」第3回「フチとエカシに昔の話を聞きに行く」(2024年12月16日開催)https://mori-kawa-umi.com/report/8874/
5)
出典:プロジェクトについて(森川海研ウェブサイト)
https://mori-kawa-umi.com/about/
